制限行為能力者とは
行為能力(単独で取引を行う資格)を制限された者を制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)といいます。
民法は、年齢または家庭裁判所の審判という形式的な基準によって一定範囲の者を定め、それらの者の行為能力を一律に制限します。
制限行為能力者は、行為能力が制限された行為(法律行為)を単独で(自己の判断のみで)行うことができません。そこで、制限行為能力者の利益を図るために保護者が付けられます。
保護者は、制限行為能力者自らがする行為に助力し(同意権)、あるいは、制限行為能力者を代理して取引を行います(代理権)。
そして、制限行為能力者が保護者の同意なしに単独で行為した場合には、保護者はその行為を取り消すことができます(取消権)。
制限行為能力者の種類
制限行為能力者は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4種類あります。
それぞれ想定される判断能力の程度に違いがあり、それに応じて行為能力の制限により保護される範囲にも広狭があります。
| 未成年者 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
|---|---|---|---|---|
| 要件 | 20歳未満の者(4条参照) | 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者(7条) | 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者(11条) | 精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者(15条) |
| 能力の範囲 | 特定の行為以外は単独でできない(5条・6条) | 日常生活に関する行為を除くすべての財産行為ができない(9条) | 13条1項所定の行為だけ単独でできない(13条) | 同意権付与の審判を受けた行為だけ単独でできない(17条) |
| 保護者 | 法定代理人(親権者または未成年後見人) | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 保護者の権限 | 同意権・代理権・取消権 | 代理権・取消権 | 同意権・取消権、付加的に代理権 | 同意権・取消権または代理権 |
未成年者
未成年者(みせいねんしゃ)とは、成年に達していない者をいいます。民法は、成年年齢を20歳とします(4条)*。
* 成年年齢を18歳に引き下げる改正法が2022年4月1日から施行されます。
未成年者の保護者は、親権者(しんけんしゃ)または未成年後見人(みせいねんこうけんにん)です。ともに未成年者の法定代理人となります。
未成年者が自ら行為するときは、原則として法定代理人の同意を要します(5条1項本文)。
例外的に、次のような行為は法定代理人の同意なしに単独で行うことができます。
- 単に権利を得、または義務を免れる行為(5条1項ただし書)
- 法定代理人が処分を許した財産の処分(同条3項)
- 営業を許された未成年者がその営業に関してする行為(6条1項)
成年被後見人
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況*にある者であって、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいいます(7条・8条)。
* 具体的には日常の買い物すら一人でできないような精神状態であって、ときどき判断能力を回復することがあっても、判断能力を欠く状態が通常であるような状況(常況)を指します。
成年被後見人には、その保護者として成年後見人(せいねんこうけんにん)が付けられます(8条)。成年後見人は、成年被後見人の法定代理人になります。
成年被後見人は、原則として自ら行為することができません。成年被後見人は、判断能力を欠く常況にあるので、成年後見人の指図どおりに行動することを期待できないからです。
したがって、たとえ成年後見人の同意を得て行為した場合であっても、その行為を取り消すことができます(9条本文)。
もっとも、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人にも行為能力が認められています(同条但書)。精神上の障害のある者であっても、日用品の購入や公共交通機関の利用など日常生活に不可欠である取引については健常者と同じように行えることが望ましいからです。
被保佐人
被保佐人(ひほさにん)とは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分*である者であって、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます(11条・12条)。
* 日常の買い物程度は自ら行うことができるけれども、重要な取引については単独で適切に行うことができない精神状態を指します。
被保佐人には、その保護者として保佐人(ほさにん)が付けられます(12条)*。
* 家庭裁判所は、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(876条の4第1項)。
被保佐人が民法13条1項各号の重要な財産行為をするには、保佐人の同意を得なければなりません。さらに、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意を要する行為の範囲を拡大することができます。ただし、日常生活に関する行為については被保佐人にも行為能力が認められます(以上、13条1項・同条2項)。
被保佐人が保佐人の同意を要する行為を単独でした場合、その行為を取り消すことができます(同条4項)*。
* 保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます(同条3項)。
被補助人
被補助人(ひほじょにん)とは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分*である者であって、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいいます(15条1項・16条)。
* 重要な取引を行うに際して誰かの援助があったほうが好ましいような精神状態を指します。その程度が深刻な場合には、補助開始の審判ではなく、保佐開始の審判の対象となります。
被補助人には、その保護者として補助人(ほじょにん)が付けられます(16条)*。
* 家庭裁判所は、特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(876条の9第1項)。
特定の法律行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けた場合*、被補助人がその行為を単独で行ったときは、その行為を取り消すことができます(17条1項・同条4項)⁑。
* 被補助人が行為能力を制限されるのは、補助人の同意を要する旨の審判を受けた場合だけにかぎられます。その審判の対象となる行為は、民法13条1項の行為の一部に限られます(17条1項ただし書)。
⁑ 家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます(同条3項)。
行為能力の制限による取消し
制限行為能力者が行為能力の制限に違反して行為した場合、本人やその保護者などがその行為を取り消すことができます*。
* 取り消すことができる行為は、一応は有効ですが、取消しの意思表示がなされることによって行為時にさかのぼって無効であったものとみなされます(121条本文)。また、追認(取消権の放棄)をすることによって確定的に有効とすることもできます(122条)。
この取消しは、取引の相手方の主観的態様(善意・悪意や過失の有無)にかかわらず認められ、また、第三者に対して主張(対抗)することもできます。
取消しの結果、取引にもとづいて給付されたものがあるときはそれを返還する義務が生じますが、このとき制限行為能力者が負う返還義務の範囲は「現に利益を受けている限度」*にかぎられます(121条の2)。これは、返還義務が取消しの実際上の障害とならないようにするためです。
* 利益が残っている限度で返還すればよいという意味であり、たとえば、何かの返済に充てたときは利益は残っているが、浪費したときは残っていない(返還しなくてよい)ことになります。
制限行為能力者の相手方の保護
行為能力の制限を理由とする取消しによって制限行為能力者の財産は手厚く保護されます。一方で、制限行為能力者と取引した相手方への配慮も必要になります。
民法は、①制限行為能力者の相手方の催告権(20条)と、②制限行為能力者が詐術を用いた場合の取消権の否認(21条)という二つの制度を設けて、制限行為能力者保護と相手方保護との調整を図っています*。
* 一般的な制度として、法定追認(125条)と取消権の期間の制限(126条)があります。
制限行為能力者の相手方の催告権
制限行為能力者側は、取引をそのまま有効とするか、それとも取り消して無効とするかを選択することができます。しかしその反面、法律関係が定まらず、取引の相手方は不安定な地位に置かれることになります。
そこで民法は、不安定な地位を解消するための手段として、相手方に催告権を与えています(20条)。
制限行為能力者の相手方は、単独で追認することができる者(行為能力者となった本人または制限行為能力者の保護者)に対して、1か月以上の期間を定めて、取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答するように催告することができます。
指定した期間内に確答があった場合は、法律関係はそのとおりに確定します(追認なら有効、取消しなら無効)。確答がなかった場合は、追認したものとみなされます*(同条1項・2項)。
* 「特別の方式を要する行為」(法定代理人が単独で同意を与えることができない行為、864条参照)について期間内に方式を具備した旨の通知を発しない場合や、被保佐人または被補助人に対して追認を得るように催告して期間内に追認を得た旨の通知を発しない場合には、行為を取り消したものとみなされます(同条3項・4項)。
なお、未成年者・成年被後見人(98条の2参照)、本人が行為能力者になった後にその保護者であった者に対する催告は無効です。
制限行為能力者の詐術
行為能力の制限を理由とする取消しは、取引の相手方が制限行為能力者を行為能力者であると信じたときでも認められるのが原則です。
しかし、制限行為能力者が相手方を騙して自らが行為能力者であると誤信させたような場合にまで制限行為能力者を保護する必要はなく、むしろ相手方の信頼を保護すべきです。
それゆえ、民法21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」と定めています。
本条が適用されるためには、詐術の結果として相手方が行為能力者であると誤信するにいたったことが必要です。相手方の誤信を惹起させた場合だけでなく、誤信を強めた場合をも含みます*。
* もっとも、単なる黙秘は詐術に当たりません(最判昭44.2.13)。

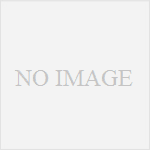
コメント