時効とは何か
時効とは、長期間継続した事実状態を正当な権利関係として認める制度をいう。その事実が真実の権利関係と合致するかどうかを問わない。
時効には、取得時効と消滅時効の2種類がある。➡取得時効 ➡消滅時効
権利を行使している状態が長期間続いた場合にその権利の取得を認めるのが取得時効であり、権利を行使しない状態が長期間続いた場合にその権利の消滅を認めるのが消滅時効である。
| 時効の種類 | 時効の基礎となる事実状態 | 時効の効果 |
|---|---|---|
| 取得時効 | 権利行使の事実状態 | 権利の取得 |
| 消滅時効 | 権利不行使の事実状態 | 権利の消滅 |
時効制度の存在理由
時効制度は、権利のない者に権利を与えたり、義務のある者の義務を免れさせたりするので、一見して不道徳な制度であるように思える。このような時効制度が存在する理由として、ふつう次の三つが挙げられる。
- 法律関係の安定(社会秩序の維持)
- 証明困難の救済
- 権利の上に眠る者は保護に値しない
① 法律関係の安定(社会秩序の維持)
長年続いた事実状態の上にはさまざまな法律関係が築かれていて、それらがくつがえされると社会生活が混乱してしまう。社会秩序を維持するためには、永続した事実状態を法律上も尊重して正当な権利関係として認めるべきである。
② 証明困難の救済
長期間継続した事実状態は真実の権利関係と合致している可能性が高いが、その反面、長い年月の間に証拠が散逸することによって権利関係を証明することが困難になることもある。
そこで、権利関係を証明することができない者(真の権利者や既弁済者)を救済するために、時効による権利の取得・消滅を認める必要が生じてくる。
③ 権利の上に眠る者は保護に値しない
長期間にわたり権利の行使を怠った者は、法の保護を受けられなくすべきであるという考えである。
時効の援用
時効は一定期間の経過によって完成するが、裁判所はそれだけでは時効によって裁判をすることができない。
時効が完成した(=時効期間が満了した)という事実に加えて、当事者が時効の利益を受ける意思を表明することが必要であり、これを時効の援用という(145条)。
これは、時効の利益を受ける(権利を取得しまたは義務を免れる)ことが当事者の良心に反する場合もあるので、時効の利益を受けるかどうかを当事者の自由な判断に委ねる趣旨である。
時効を援用するか否かは各当事者の自由であるから、その効果は援用した者についてのみ生じ、援用しない他の者には影響が及ばない(援用の効果の相対性)。
時効を援用することができる者(援用権者)は、時効によって直接に利益を受ける者(およびその承継人)にかぎられる(大判明43.1.25)。
債権の消滅時効の場合は債務者(連帯債務者)が、所有権の取得時効の場合は目的物の占有者が援用権者になる。そのほかにどのような者が援用権者となりうるかが、とくに消滅時効について問題となる。
この点について民法145条は、保証人(連帯保証人を含む)、物上保証人*、第三取得者⁑を(主たる債務や被担保債権の)消滅時効の援用権者の例として列挙している。
* 自己所有の不動産に他人の債務のための抵当権を設定した者。
⁑ 担保権が設定された不動産を取得した者。
判例は、仮登記担保権に劣後する抵当権者が予約完結権の消滅時効を援用すること(最判平2.6.5)や、詐害行為の受益者が債権の消滅時効を援用すること(最判平10.6.22)を肯定する。しかし、後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することを否定している(最判平11.10.21)。
時効の利益の放棄
時効の完成によって得られる利益(権利の取得や義務の消滅)は、当事者(援用権者)が一方的な意思表示によって放棄することができる。時効の援用と同じく、時効の利益を受けるかどうかについて当事者の意思を尊重する趣旨である。
ただし、時効の利益の放棄が認められるのは時効完成後にかぎられており、時効完成前の放棄は無効とされている(146条「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」)。時効完成前の放棄を認めると、債権者が債務者の窮迫状態に乗じて強制的に放棄を約束させるおそれがあるからである。
時効の利益の放棄をした後は、その時効を援用することができなくなる。もっとも、放棄の効果も援用の効果と同じように相対効であって、放棄をしなかった者には影響が及ばない。
債務者が債務の承認や一部弁済といった債権の存在を前提とする行為(自認行為という)をしても、債権の消滅時効の完成を知らないかぎり、その行為は放棄として認められないと解されている。
それでは、時効完成の事実を知らずに債務の承認をした債務者が、その後に消滅時効の援用をすることは許されるであろうか。債務者が矛盾した主張をすることや、債権者に生じた信頼を保護すべきことを考えれば、援用を許すことは適当でない。
判例も、信義則を根拠に、時効の援用をすることは許されないとしている(最大判昭和41.4.20)。
時効の効果――遡及効
時効の効果は、取得時効の場合は権利の取得であり(162条・163条)、消滅時効の場合は権利の消滅である(166条)。
これらの時効の効果は、時効期間の起算日にまでさかのぼって発生する(144条)*。
* 債権の相殺についての例外がある(508条)。
これによって、たとえば土地の所有権を時効取得した者は、その占有を開始した時から所有者であったことになる。また、時効消滅した債権の債務者は、時効期間中に発生した利息や遅延損害金を支払う義務をも免れることになる。

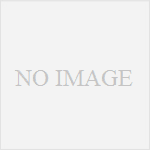
コメント