民法110条適用の要件
民法110条は、代理人がその権限外の行為をした場合の表見代理(権限外の行為の表見代理、権限踰越の表見代理などともいう)について規定する。110条の表見代理が成立するための要件は、次のとおりである。
- 代理人に何らかの権限が与えられていたこと(基本代理権の存在)
- 権限の範囲を越えた代理行為が行われたこと
- 第三者(相手方)が代理権があると信じたことに正当な理由があること
(1) 基本代理権の存在
民法110条が適用されるためには、無権代理人が何らかの権限を有していたことが必要である。この何らかの権限のことを基本代理権と呼ぶ。代理人に対して基本代理権を与えたという点に本人の帰責性が認められる。問題は、どのような権限が基本代理権として認められるか(どのような権限を与えた場合に本人の責任を問えるのか)であって、判例上、問題となったものとして、公法上の行為についての代理権、事実行為をする権限などがある(後述)。無権代理人が何らの権限をも有していない場合には、110条の表見代理は成立しない。
(2) 権限の範囲を越えた代理行為が行われたこと
民法110条は、無権代理人が基本代理権の範囲を逸脱して無権代理行為を行った場合に適用される。無権代理人のした権限外の行為は、基本代理権と同種同質の行為でなくてもよい(大判昭5.2.12)。無権代理人が直接本人の名を記して代理行為を行った場合(いわゆる署名代理)にも、本条が類推適用される(最判昭51.6.25)。
(3) 正当理由の存在
第三者(取引の相手方)が保護されるためには、第三者が代理人に権限があると信じたことについて「正当な理由」(正当理由)が存在することが要件となる。従来の理解によれば、「正当な理由」は相手方の善意無過失と同義である。どのような事実がある場合に正当理由が認められるか、その判断基準が問題となる。
基本代理権の認定
公法上の行為ついての代理権
民法110条が適用される基礎として、本人から無権代理人に対して何らかの権限が与えられていたことが必要である。どのような権限が授与されていた場合に基本代理権と認定されるが問題であるが、判例上問題となったものとして、公法上の行為についての代理権や事実行為の委託などがある。
判例は、取引の安全を目的とする表見代理制度の趣旨に照らして、基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要し、公法上の行為についての代理権はこれに当たらないとする(最判昭39.4.2―印鑑証明書下付申請行為の代理権を与えたが代理人が抵当権設定契約をしたという事案において表見代理の成立を否定)。
しかし一方で、公法上の行為が私法上の取引行為の一環としてなされるものである場合には、代理人の権限の外観に対する第三者の信頼を保護する必要があるから、基本代理権となることを認めている(最判昭46.6.3―贈与契約上の義務の履行のために登記申請行為を委任された者が連帯保証契約を締結したという事案で、登記申請行為が私法上の契約による義務の履行のためになされるときは基本代理権となると判示した)。
事実行為の委託
判例は、基本代理権とは、代理権、すなわち法律行為を行う権限であるとし、事実行為の委託を基本代理権の授与として認めない(最判昭34.7.24―取締役の印鑑を預っていた経理係が取締役個人名義の保証契約を締結した事案、最判昭35.2.19―勧誘員である父親から一切の勧誘行為を任されていた長男が父親を保証人とする契約を締結した事案)。
これに対して、学説は、基本代理権を法律行為の代理に限定せず、事実行為を含めてなんらかの行為を代行する権限であると捉えている。そもそも、民法110条が基本代理権の存在を要求しているのは、本人に帰責性があること、すなわち、本人に責任を負わせる前提として本人が代理権が存在するかのような外観の作出に関与したという事実が重視されるからである。そうであるならば、法律行為以外の行為の委託であっても、重大な権限を有するような外観を作出することがありえる以上、そのような行為の委託を基本代理権から除外するのは適当ではない。基本代理権の存在を広く認定したうえで、正当理由の判断において委託した行為と実際になされた行為とのかい離度合を考慮する見解が有力である。
正当理由の判断
正当理由の意味
民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理人が権限の範囲内で行為したと信じたことについて正当な理由(正当理由)が存在しなければならない。この正当理由は、従来、権限外行為であることについて相手方が善意・無過失であるという意味に解されてきた(最判昭44.6.24)。ただし、実際の正当理由の判断にあたっては、さまざまな事情が総合的に考慮されている。
現在の学説は、基本代理権を広く認定するので、相手方側の事情だけでなく、本人側の事情も正当理由の有無を判断する一要素として考慮する。この考え方によれば、前述したように、本人が代理人に委託した行為と代理人が実際に行った行為とのかい離の程度などは、正当理由の判断において考慮されることになる。
〔参考〕本人の過失の要否
民法起草者は、フランス民法にならい、110条の適用につき、基本代理権の存在のほかに本人の過失が必要であると考えていた。しかし、その後、取引安全を重視する傾向が強まるなかで、本条適用の要件として本人の過失は不要であると解されるようになり、判例も通説に従うようになる(最判昭34.2.5)。
正当理由の判断基準
(1) 実印や印鑑証明書の所持
不動産の処分や保証契約などの取引において、代理人が本人の実印や印鑑証明書(不動産取引においてはさらに登記済証)を所持していた場合は、相手方は代理人が本人から権限を与えられたと信じるのが通常であるから、正当理由が認められやすい。ただし、代理人と本人が夫婦など同居の親族であるようなときには、実印等の濫用が容易であるのがふつうなので、簡単には正当理由を認めることはできない。
(2) 代理権の存在を疑わせるような事情
たとえば、取引が代理人の利益にしかならない、本人に著しく不利な条件であるなどのように代理人が権限を有することを疑わせるような事情がある場合には、相手方は本人に直接照会するなどの手段によって本人の意思あるいは代理権の有無を確認すべきであって(調査義務)、それをしなかったときには正当理由が認められない(前掲最判昭51.6.25―A社の代表BがCの実印と印鑑証明書を利用してCがA社のD社に対する債務の保証人となる契約を締結した事案で、D社がCの保証意思の確認を怠ったとして正当理由を否定した)。
正当理由の証明責任
正当理由を相手方(第三者)の善意無過失と捉える立場(判例)によると、相手方がその証明責任を負うことになる。民法109条の善意無過失について本人が証明責任を負うとされていることと対照的である。
これに対して、正当理由を本人の事情と相手方の事情との総合的要件であると考える立場では、正当理由を基礎づける事実ごとに本人と相手方のどちらが証明責任を負うかが異なってくる。実印の所持など代理権の存在を推測させる事実は相手方が主張立証することになるが、代理権の存在を疑わせる事情のような正当理由を否定する事実については本人が主張立証しなければならない。
民法110条の適用範囲
法定代理への110条適用の可否
民法110条は、文言上、法定代理への適用を否定していない。従来の通説は、取引の安全を重視して、本条の法定代理への適用を肯定していた。しかし、本人自らが他人を信頼して権限を与えたところに本人の帰責性が認められるとするならば、本人の意思によらずに代理権が与えられる法定代理の場合には本人の帰責性を問うことができない。したがって、現在の学説では、本条は法定代理の場合には適用されないとする見解が有力である。
判例には、戦前のものであるが、110条を法定代理の場合に適用したものがある(大連判昭17.5.20―親権者が親族会の同意を得ずに子を代理した事案)。また、民法761条について、同条は日常の家事に関する夫婦相互の代理権を定めたものであるとしつつ、その日常家事代理権を基礎として110条の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なうおそれがあり相当でないとした判例がある(最判昭44.12.18―夫が妻の特有財産である不動産を勝手に売却した事案)。
〔参考〕民法110条の趣旨の類推適用
「夫婦の一方が(略)日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である」(最判昭44.12.18―事案の解決としては、110条の類推適用を否定した。)
法人の代表と110条の適用
法人の代表権は定款などによって制限することが可能であり、法人の代表者がその内部制限に違反して法人としての行為を行った場合は無権代理行為となる。ただし、代表者と取引をした相手方を保護するため、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者(相手方)に対抗することができないと定められている(一般法人法77条5項、会社法349条5項)。たとえば、定款によって、代表者がある一定の取引を行うに際して理事会の承認決議を必要とする旨の制限が定められていた場合であっても、取引の相手方がそのような制限を知らなかったときは、法人は相手方に対して内部制限の存在を理由として無権代理であることを主張することができない。
もっとも、上記の第三者保護規定は、相手方が理事会の承認決議を必要とするという代表権の制限の存在を知らなかった場合について適用されるのであって、代表権の制限の存在を知ったいたが、その理事会の承認があったものと信じた場合には適用されない。後者の場合において、判例は、第三者(相手方)において、代表者が理事会の承認を得て適法に法人を代表する権限を有するものと信じ、かつ、そう信じるにつき正当の理由があるときには、民法110条の類推適用によって法人は代表者の行為について責任を負うとする(最判昭60.11.29)。
110条の「第三者」の範囲
判例は、民法110条の第三者は、代理行為の直接の相手方にかぎられ、相手方からの権利の転得者を含まないとする(最判昭36.12.12―代理人の越権で手形が振り出された場合、被裏書人がたとえ正当理由を有していても、110条は適用されない)。表見代理は代理権の存在を信頼した者を保護するための制度であるが、転得者が積極的に信頼したのは、前主の権利が正当であることであって、代理権が存在することではないからである。前主が正当な権利者であることに対する信頼は、即時取得(192条)など他の制度によって保護される。
民法109条または112条との重畳適用
(1) 109条と110条の重畳適用
本人が第三者(取引の相手方)に対して他人に代理権を授与した旨を表示した場合、表示された代理権の範囲内において無権代理行為が行われたのであれば、民法109条適用によって表見代理が成立する。これに対して、無権代理行為が表示された代理権の範囲を逸脱して行われたときには109条適用の要件を欠くことになる。しかし、判例は、そのような場合であっても、本人は、109条と110条によって無権代理行為につき責任を負うことを認めている(最判昭45.7.28)。
(2) 110条と112条の重畳適用
代理権が消滅した後に代理行為がなされた場合、消滅した代理権の範囲内の行為であれば、民法112条の適用によって表見代理が成立する。無権代理行為が消滅した代理権の範囲外であっても、110条と112条の「両規定の精神に則りこれを類推適用して」無権代理行為につき本人が責任を負うとするのが判例である(大連判昭19.12.22)。

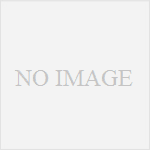
コメント