法人格のない団体の規律
社会の構成単位として活動している団体のなかには、法人格(権利能力)を有しないものも存在します。そのような法人格のない団体をめぐる法律関係をどのように処理すべきかが問題となります。
団体関係を規律する民法上の規定としては、組合に関する規定(667条~688条)があります。しかし、民法上の組合は当事者間の契約としての性格が強い団体を想定しているので、法人格のない団体すべてに組合に関する規定を一律に適用することは妥当ではありません。
法人格のない団体のなかには社団法人と同様の実体を有する団体も存在する*のであり、そのような団体についてはできるかぎり社団法人に準じた扱いをするのが適切です。
* このような団体が法人格を有しない理由としては、団体があえて法人格を取得しない場合や、法人となるために設立中の団体である場合が考えられます。設立中の団体については、法人の設立に関する規定が整備されている以上、法人格の欠如はとくに問題になりません。
判例も、ある団体が「権利能力なき社団」といえる場合について、社団法人に準じて処理することを認めています。
伝統的な考え方によれば、およそ団体は法人となるのにふさわしい団体である社団と、そうでない団体である組合とに二分されます。そして、ある団体が社団であれば社団法人に関する規定を適用(類推適用)し、組合であるならば組合の規定を適用します。
社団は、団体そのものが個々の構成員から独立して存在しているような団体です。個々の構成員は、団体を通じて間接的に結合しており、はじめから変動することが予定されています。
組合は、当事者間で共同事業を営むことを約束することによって成立する団体です(667条1項)。各構成員(組合員)は契約によって相互に義務づけあう関係にあり、構成員の個性が重視されます。
このような社団と組合の二分法に対しては、ある団体が社団と組合のいずれであるかを二者択一的に判断していずれかの規定群を一括して適用するのではなく、団体の実態にあわせて社団・組合の規定を選択的あるいは混合的に適用すべきであるとする考え方も主張されています。
権利能力なき社団
判例・学説は、社団法人に準じた法的取扱いをすべきである団体を権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)と呼んで、その他の団体と区別します。
判例によれば、権利能力なき社団とは、「①団体としての組織をそなえ、②そこには多数決の原則が行なわれ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかして④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの」を指します(最判昭39.10.15)。
権利能力なき社団の効果
ある団体が権利能力なき社団であると認定されることによって、具体的にどのような効果が生じるのか。判例によって認められた効果として、次のようなものがある。
- 権利能力なき社団の財産は構成員に総有的に帰属する(前掲最判昭39.10.15、最判昭32.11.14など)。
- 不動産登記について、社団は登記請求権を有せず、代表者個人の名義による登記のみが認められる(最判昭47.6.2)。
- 社団の債務について、社団(構成員全員)の総有財産だけが責任財産となり、構成員各自は直接には責任を負わない(有限責任、最判昭48.10.9)。
団体の権利・義務の総有的帰属
社団の財産や社団の代表者が社団の名において行った取引の効果は、その社団の構成員全員に総有的に帰属します(上掲最判昭39.10.15、上掲最判昭48.10.9)。総有的帰属という構成をとるのは、実質的に団体自身に権利義務が帰属するのと同様の結論を導くためです。
総有という構成をとる帰結として、社団の構成員は、当然には、社団財産の上に持分権や分割請求権を有しません(上掲最判昭32.11.14)。
団体名義での不動産登記の可否
権利能力なき社団の不動産は形式的には構成員全員の総有に属し、社団自身は不動産の権利主体ではありません。したがって、社団は登記請求権を有せず、不動産の登記名義人になることは認められません*。
* 社団の代表者である旨の肩書をつけた登記(たとえば、「A社団代表理事B」)も認められません(上掲最判昭48.10.9)。
そこで、社団の不動産を信託的に代表者個人の所有として、代表者が個人の名義で登記をする方法が認められています(上掲最判昭47.6.2)*。
* 構成員全員の共有名義で登記をする方法もありますが、社団の構成員は変動することが予定されているので現実的ではありません。
法人格否認の法理
法人とその構成員である社員は、法律上は別々の法主体として扱われます。
その帰結として、社員が法人の代表として行った行為の効果は法人に帰属して社員個人はその責任を負うことはなく、また、社員が個人名義で行った行為の効果は法人には帰属しないのが原則です。
しかし、世の中には、法人の形態をとっていてもその実質が個人企業にすぎず、法人として取引したのか、それとも代表者である社員が個人として取引したのかが判然としないことが多いような企業体も存在します。
このように法人格がまったくの形骸にすぎない場合にまで、法人とその社員とを別個の法主体として認めることは、取引の相手方を害するおそれがあり、適当ではありません。
そこで、そのような場合に、問題となる法律関係に関するかぎりにおいて、法人という法形式を無視し、法人と背後の利用者である社員(自然人または法人)とを同一視して扱おうとする考え方があります。これを法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)といいます。
法律上の規定はありませんが、判例によってこの法理が確立されています(最判昭44.2.27)。
法人と社員とが同一視される結果、法人の債権者は社員に対して責任を追及することができるようになり*、また、社員が個人名義でした行為を法人の行為として扱うことができるようになります。
* 法人格の「否認」といっても、法人格が否定されて法人としてなした行為が無効になるわけではありません。

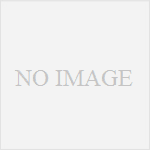
コメント