不動産と動産
物は、法律上さまざまな視点によって分類される。とりわけ重要なのは、不動産と動産の分類である*。
* 不動産と動産とでは、公示方法(177条・178条)、公信力の有無(動産について192条)、無主物の取扱い(239条)、物権の種類の違い(用益物権・抵当権は動産の上には成立しない)などに関して法的な取扱いが大きく異なる。
不動産
不動産とは、土地およびその定着物をいう(86条1項)。
土地
土地は、地表だけでなくその上下を含む(207条参照)。地中の岩石や土砂は、土地の構成部分となる。
土地は自然には連続しているが、人為的に区画されて一筆(土地の単位)ごとに登記される。一筆の土地を分割して複数筆の土地にしたり(分筆)、隣接する土地を合わせて一筆の土地としたり(合筆)することも可能である。
一筆の土地の一部を時効取得すること(大連判大13.10.7)や、一筆の土地の一部を分筆前に譲渡することも認められる(最判昭30.6.24)。
土地の定着物
土地の定着物とは、現に土地に固定されており、取引観念上その状態で使用されるものをいう。具体的には、建物、樹木、地盤に据え付けられた機械などがこれに当たる。
原則として、土地の定着物はその地盤である土地と一体のものとして扱われ、独立の不動産とはならない。つまり、土地の所有権に吸収され、土地の処分(譲渡・抵当権設定)に従う(242条・370条参照)。
しかし、次のように、土地の定着物でありながら土地とは独立の取引の客体となる物も存在する。
建物
建物は、つねに土地とは別個独立の不動産として扱われる。このことを直接規定した条文はないが、不動産登記法が土地と建物を区別して扱っていることから明らかである。
建築中の建物であっても、登記可能な状態になれば、独立の不動産として評価される*。そのためには、屋根と周壁を有していれば足り、床や天井はまだ備えていなくてもよいとされる(大判昭10.10.1)。
* 独立の不動産として評価される前の状態を「建前」という。判例は、建前を動産として扱う(最判昭54.1.25)。
樹木(立木)
樹木(立木)は、原則として土地の一部として扱われるが、一定の公示方法を備えることによって植栽されたままの状態でも土地とは独立の不動産として取引の客体とすることができる。
個々の樹木の公示方法として明認方法があり、樹木の集団の公示方法として明認方法のほか立木法による登記(立木ニ関スル法律1条)がある*。
* 立木に抵当権を設定するためには、立木法による登記が必要である。
未分離の果実
果実がその収穫期に近づいたときは、樹木や土地と未分離の状態のままで独立の動産として取引の客体とすることができる(大判大5.9.20)。
動産
不動産以外の物は、すべて動産である(86条2項)。
金銭(貨幣)は、動産の一種であるが、流通手段としての機能を有することから、特別な取扱いを受ける。
すなわち、金銭を占有する者は、その原因を問わず、その所有者であるとされる(最判昭39.1.24)。盗取により占有を取得した場合であっても、金銭の所有者となる。
このように金銭には、動産に関する規定(176条・178条・192条)が適用されない。
主物と従物
ある物の経済的効用を助けるために他の物がそれに付属させられているとき、前者を主物といい、後者を従物という(87条1項)。
たとえば、家屋を日常的に使用するために畳を敷いて建具(障子・ふすまなど)を取り付けた場合、家屋と畳・建具は主物と従物の関係になる。
主物と従物の関係
民法87条2項は、「従物は、主物の処分に従う」と規定する。従物と主物は互いに独立した物であるが、この規定により法律的運命をともにすることになる。
家屋(主物)を譲渡した場合、その畳・建具(従物)も家屋と一緒に譲渡される。
従物の扱いは当事者が取引に際して取り決めておくことがふつうだが、そのような取り決めがなされていない場合にこの規定が適用される。つまり、87条2項は、当事者の通常の意思の推測にもとづく任意規定である(通説)*。
* 87条2項と似たような規定に370条がある。抵当権の効力が従物に及ぶことの法的根拠をどちらの条文に求めるかという問題がある。
従物の要件
ある物が従物であるための要件は次のとおりである(87条2項参照)。
- 主物から独立した物であること*
- 主物の常用に供されること(主物の経済的効用を継続的に助けること)
- 主物に付属していること(主物と場所的に近接していること)⁑
- 主物の所有者の所有に属すること⁂
* 独立の物かどうかは、単にその物が取り外し可能かどうかだけでなく、その効用も考え合わせて判断する必要がある。建物に備え付けられた畳や障子のように、取り外しが自由であるものは独立した物であるといえる。しかし、取り外し可能な建具であっても、雨戸や入口の扉のように建物の内外を遮断する効用を果たすものは、壁と同じように建物の一部を構成し、独立の物ではない(大判昭5.12.18)。
⁑ 従物は、主物と物理的に接着している必要はなく、主物の効用を助けることができる場所にあればよい。たとえば、ガソリンスタンドにある地下タンクなどの諸設備は店舗用建物の従物である(最判平2.4.19)。
⁂ 87条1項の法文や当事者意思の推測という趣旨に忠実な解釈である。判例も、主物・従物ともに同一の所有者に帰属することが必要であるとする(大判昭10.2.20)。これに対して、従物が他人の所有物の場合にも本条の適用を認める見解も有力である(従物に関しては他人物売買となる)。
従たる権利
物ではなく権利であっても、従物に準じた扱いをするのが適当なものもある。これを従たる権利と呼ぶ。
たとえば、借地上の建物の譲渡は借地権の譲渡をともなう(最判昭47.3.9)。また、借地上の建物に設定された抵当権の効力は敷地の賃借権に及ぶ(最判昭40.5.4)。
元物と果実
元物(げんぶつ、がんぶつ)とは、収益を生じさせる物をいう。元物から生じる収益が果実である。
果実には、天然果実と法定果実の2種類があり、それぞれ帰属のしかたが異なる。
天然果実
天然果実とは、物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。
たとえば、農作物、鉱物、計画的に伐採される材木がこれに当たる。
天然果実は、原則として元物から分離するときに独立の物となる。
天然果実の帰属
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する(89条1項)*。収取権者は、元物の所有者または地上権者・永小作権者などである。
* 未分離果実が独立の取引客体となる場合、本規定は適用されない。
妊娠した馬を買い取った後に子馬が生まれた場合、子馬の所有権は出産時の親馬の所有者である買主に帰属する。
法定果実
法定果実とは、物の使用の対価*として受けるべき金銭その他の物をいう(88条2項)。
* 元物そのものの利用によって得られる利益(使用利益)とは異なる。
たとえば、家賃・地代(不動産使用の対価)、レンタル料(動産使用の対価)、利子(元本使用の対価)がこれに当たる。
法定果実の帰属
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する(89条2項)。
賃貸中の建物を売買する場合、所有権移転前の賃料(法定果実)は売主に、移転後の賃料は買主に帰属する。
その他の物の分類
物には、これまでに述べた分類のほか、可分物・不可分物*、代替物・不代替物⁑、特定物・不特定物⁂などの分類もある。
* 物の性質または価値を著しく損なわずに分割できる物(例、金銭、土地)を可分物といい、そうでない物(例、動物、自動車)を不可分物という。
⁑ 取引上一般に個性を問題とせず、種類・品質が同じ物で代えられる性質の物(例、金銭、米)を代替物といい、取引上一般に個性があり、他の物で代えることができない性質の物(例、土地、美術品)を不代替物という。
⁂ 具体的な取引の際に当事者が物の個性に着目したときのその物(例、「この馬」と指定したとき)を特定物といい、そうでない物を不特定物(例、「馬10頭」と注文したとき)という。

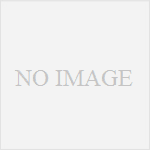
コメント